令和5年5月16日(火)に「科学の甲子園」桐陽チームの第一回研修会が開催されました。参加生徒は1年生が11名、2年生が8名の計19名です。「科学の甲子園」福島県大会への出場はSTEAM教育の一環で、本校では3年目の取り組みとなります。担当者から「科学の甲子園」の概要や今後の活動について説明があり、参加生徒は「科学の甲子園」についての理解を深め、また、出場メンバー同士の交流を図ることができました。
生徒たちは今秋開催予定の「科学の甲子園」福島県大会に向けて個別研修やチーム研修に励みます!
概要説明 
2年生チーム自己紹介

1年生チーム自己紹介


参加理由
・去年参加して多くのことを経験できたから。
・化学が好きで、多くの学びを得られると思ったから。
・前回挑戦してみて、大会に向けてみんなで頑張ったり、一生懸命取り組んだことが楽しかったから。
・科学に関する事業だったので興味を持ったから。など
令和5年5月12日(金)に「医療系進学ガイダンス」が行われました。2年生25名、3年生8名の計33名が参加しました。講師は毎年お世話になっている、国際医療福祉大学 医療福祉学部 学部長 山本康弘教授です。チーム医療・チームケアの観点から「きっと見つかる!自分にあった専門職~医療福祉のスペシャリスト~」という題でお話しいただきました。山本先生の丁寧でたおやかな口調と的確な講演内容はいつも勉強になります。「毎年熱心に聞いてもらって感心します」と本校生の聴講態度にお褒めの言葉もいただきました。


《生徒の感想》
・医療にはこんなにもたくさんの専門職が関わっていることが分かりました。私は看護士の話が目的でガイダンスに参加しましたが、言語聴覚士や診療放射線技師、作業療法士などのたくさんの専門職のことを聞いて、その違いを知ることができました。いろいろな道を考えてみることも大切だと思いました。
・講義を聞き、自分が迷っている2つの職業について聞くことができて良かったです。自分の進路目標を達成するためにどのようなことをしたらよいかを明確にできる講義内容でとてもためになりました。
・今回の講座を受けて、時代が変わってきているのだと改めて実感しました。チーム医療についてよく知ることができました。初めて耳にした診療情報管理士にも興味が湧きました。
・すべての医療関係の職業は人と密に関わり合う職業なので、笑顔で人と接することや人の気持ちを理解する力を身に付けるなど、今からできることを実践していきたいと思いました。
今年度の公務員対策講座が始まりました。4月27日(木)放課後、ケイセンビジネス公務員カレッジの竹田 佑樹 氏を講師に迎え、第1回対策講座を実施しました。公務員希望者6名が参加しました。この講座は今後、7月まで数回実施します。

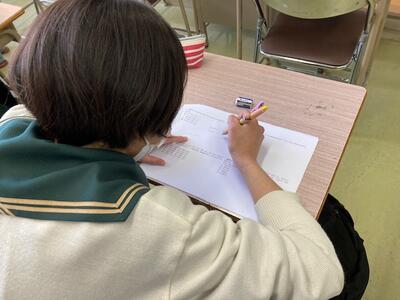

大学受験もそうですが、公務員試験も簡単には受かりません。例えば、昨年度の須賀川市の採用試験(高校卒程度)の競争率は4.9倍、令和3年度は6.0倍です。(須賀川市ホームページより)万全の対策が必要です!
4月12日(水)に「専門学校ガイダンス」と「公務員ガイダンス」を実施しました。どちらも早期の進路意識向上を目的としています。専門学校ガイダンスには29名、公務員ガイダンスには15名が参加しました。
〇専門学校ガイダンスの様子
講師:株式会社さんぽう 朝生 浩章 氏

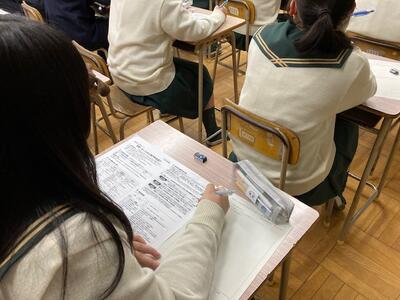

〇公務員ガイダンスの様子
講師:ケイセンビジネス公務員カレッジ 竹田 佑樹 氏


桐陽高校では生徒の進路決定や意識向上を目的としたガイダンスを年間とおして計画しています。話を聞いてみないと分からないことがたくさんあります。ぜひ参加して自分の可能性を広げて下さい。